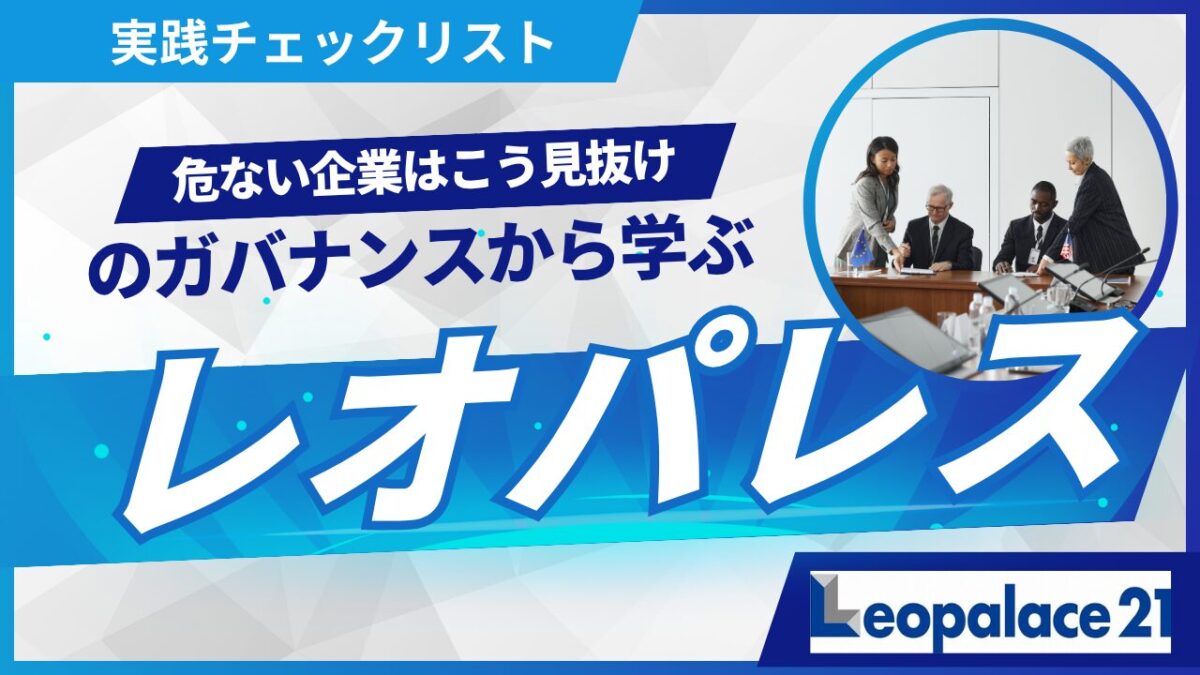「上場企業だから安心」「名前を聞いたことがあるから大丈夫」
――そんな感覚で投資していませんか?
私たちは株式投資をする際、つい「業績」や「配当」「チャート」ばかりに目がいきます。
ですが、実はもっと重要なのが、企業の“中身”、つまり「ガバナンス(企業統治)」です。
上場企業でも、ガバナンスに問題があれば、経営は迷走し、不祥事が起き、株価が暴落する可能性があります。
しかもそれは、表面の数字ではなく「企業の開示情報」や「統治構造」を読み解くことで事前に見抜けるのです。
その実例として、今回はかつて不動産投資銘柄として人気を誇ったレオパレス21(証券コード:8848)を取り上げます。
2018年、同社は施工不良問題で社会的批判を浴び、業績も株価も大きく揺らぎました。
しかし、その兆候はずっと前から、企業ガバナンスの構造に現れていたのです。
本記事では、有価証券報告書や東証の開示資料をもとに、レオパレス21の「ガバナンス上の異常」を読み解き、同様の企業を見抜くチェックポイントを提供します。
投資で勝つには、買う前に「避けるべき企業」を知ることが何より重要です。
今後あなたがリスクの高い企業を掴まないために、この記事が役立てば幸いです。
1.創業者色が抜けきれていなかった経営体制
レオパレス21は、1973年に深山祐助氏によって設立されました。
長らく“創業者主導”で急成長を遂げてきた同社ですが、その一方で、経営の中枢が創業家の影響下にあり続けたことが、後のガバナンス不全に繋がったと見る専門家も少なくありません。
実際、創業から約40年以上にわたり、代表取締役社長のポストは創業者本人か、創業者に近い人物に限定されてきたのが実情です。
たとえば、深山祐助氏が退任した2006年以降も、同社の経営は「創業家の影響力を引き継いだ人材」が中心でした。
2015年に社長に就任した深山英世氏は、深山祐助氏の実子であり、“実質的な創業家支配”が継続していた構図といえます。
こうした体制では、「経営判断が独善的になりやすい」「社内からの異論が通りにくい」といったリスクが高まりやすくなります。
実際、後に大きな問題となった「アパート施工不良」についても、社内で長年にわたり黙認されていたという報道があります。
「現場では問題が共有されていたが、経営層には届かなかった」
― これは、経営が閉鎖的な文化で運営されていたことを示す象徴的な構図です。
さらに、有価証券報告書(2017年3月期)によれば、当時の取締役の構成は以下のとおりです:
- 代表取締役社長:深山英世(創業者の実子)
- 取締役6名中5名が社内出身者
- 社外取締役の選任は1名のみ(かつ不動産業界経験者)
つまり、経営陣の多くが創業家またはその息がかかった人材で占められており、「外部の視点」や「牽制力」が著しく欠如していたことがうかがえます。
これは東証が提唱する「コーポレートガバナンス・コード」が強く推奨する「経営の多様性」や「監督と執行の分離」に明確に反する状態です。
🔎 ポイントまとめ
- 創業者の支配が長期化 → 経営の透明性が損なわれやすい
- 社内昇格者中心の経営体制 → 内部牽制が機能しづらい
- 社外取締役が名目上だけの存在 → 意思決定が独善的になるリスク
2.施工不良問題と社外取締役の“機能不全”
レオパレス21における最大のガバナンス崩壊事例として知られているのが、2018年に発覚した大規模なアパート施工不良問題です。
この問題では、1996年から2010年にかけて建築された1万4,000棟以上の物件で、耐火性・遮音性などの建築基準を満たしていない施工が行われていたことが明らかになりました。
驚くべきは、この問題が十数年にわたり社内で黙認され、取締役会レベルで是正されることがなかった点です。
つまり、取締役会や社外取締役が「機能不全」に陥っていた可能性が極めて高いのです。
🔍 社外取締役の経歴と構造的な偏り
2017年3月期の有価証券報告書によると、同社の取締役構成は以下の通り:
- 取締役(社外):1名
- その社外取締役の経歴:不動産金融業界出身/非常勤
- 取締役7名中6名が社内出身・執行役員を兼任
この構造は、名目上「社外取締役制度」を導入しているように見えても、実質的に経営監督が働いていないことを意味します。
特に問題なのは以下の2点:
- 社外取締役が非常勤であり、社内の詳細な実態にアクセスしづらい立場にあったこと
- その人物が不動産業界の延長線上にいる人材であり、「外部からの視点」や「異分野からの牽制力」を持ちにくかったこと
つまり、形だけの“お飾り的な社外取締役”となっていた疑いが極めて強いのです。
📉 施工不良の“兆候”はなかったのか?
2018年2月、同社はようやく自主的に社内調査を開始し、「過去に建築基準法に違反した施工があった」と発表。
しかし、実際にはそれより前の段階で、現場担当者レベルでは問題を認識していたと複数のメディアが報じています(参考:朝日新聞 2018年3月1日報道)。
「10年以上前から同じ問題が繰り返されていたが、改善されなかった」
― 元社員の証言(NHKスペシャル 2019年)
これは、内部からの声が経営層に届いていなかった、あるいは届いても取締役会が機能していなかった可能性を示しています。
つまり、形式上はガバナンス体制を備えていたが、実質的には“チェック&バランス”が破綻していたということです。
📌 ポイントまとめ
- 社外取締役が非常勤かつ業界関係者 → 独立性に欠ける
- 内部からの問題提起が取締役会に届かなかった
- 経営の牽制役(社外取締役)が「在籍しているだけ」の状態だった
- 結果として10年以上にわたって施工不良が見過ごされ、社会的信用を失った
この事例は、社外取締役という制度があっても、「人選」や「機能性」が不十分であれば何の意味もないことを如実に物語っています。
投資家としては、「社外取締役がいるかどうか」ではなく、
「どういう人物が、どのような立場で、どのくらい関与しているのか」まで見る必要があるのです。
このように、レオパレス21の実例からは、ガバナンス体制が“あるように見えて機能していない”企業がいかに危険かが浮き彫りになります。
📌 ポイントまとめ
- 社外取締役が非常勤かつ業界関係者 → 独立性に欠ける
- 内部からの問題提起が取締役会に届かなかった
- 経営の牽制役(社外取締役)が「在籍しているだけ」の状態だった
- 結果として10年以上にわたって施工不良が見過ごされ、社会的信用を失った
この事例は、社外取締役という制度があっても、「人選」や「機能性」が不十分であれば何の意味もないことを如実に物語っています。
投資家としては、「社外取締役がいるかどうか」ではなく、
「どういう人物が、どのような立場で、どのくらい関与しているのか」まで見る必要があるのです。
このように、レオパレス21の実例からは、ガバナンス体制が“あるように見えて機能していない”企業がいかに危険かが浮き彫りになります。
3.内部通報制度の形骸化
企業が不祥事を防ぐためには、内部の人間が「声を上げられる仕組み」と「それを真摯に受け止める体制」が不可欠です。
いわゆる「内部通報制度(ホットライン)」は、上場企業のガバナンスにおける重要な柱の1つとされています。
しかし、レオパレス21においては、この制度が形式的に存在していたものの、実際には機能していなかった可能性が極めて高いことが、各種報道から明らかになっています。
🔍 社員は「施工不良の存在」に早くから気づいていた
2018年に大規模な施工不良問題が表面化した際、複数の元社員がメディア取材に対して以下のような証言をしています:
「2015年の時点で、天井裏の施工不備を現場で確認していた」
「部内で共有されていたが、“問題にするな”という空気があった」
―(NHKクローズアップ現代+、2019年3月放送)
また、朝日新聞(2018年3月1日付)も以下のように報道しています:
「施工基準に適合していない構造の存在が、技術担当部門では2007年頃から認識されていた」
つまり、現場の最前線では10年以上前から問題の存在が共有されていたにもかかわらず、それが経営陣や取締役会に正式に報告されることはなかった、あるいは報告されても握りつぶされた可能性があるのです。
📄 有価証券報告書における「内部通報制度」の実態
2017年3月期の有価証券報告書では、同社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に以下のような記載があります:
「法令違反行為を早期に発見・是正するため、内部通報制度を設置し、社員等からの通報に対応している」
一見、ガバナンス的に問題がなさそうに見えますが、肝心の「通報の受付先」が社内の人事部門に限定されていたことや、社外の独立した第三者機関ではなかったことが後の第三者委員会調査で指摘されています(2019年第三者委員会報告書より)。
このような構造では、通報者が不利益を被ることを恐れて声を上げづらくなり、通報があっても上層部に握りつぶされる可能性が高まります。
❗ 企業は「制度があること」より「それが機能しているか」が重要
レオパレス21の例は、「内部通報制度は整備している」と開示していても、運用実態が伴っていなければ全く意味がないことを示しています。
これは、形式だけを整えたガバナンス体制では、企業不祥事の防止には不十分であるという、極めて重要な教訓です。
📌 投資家の視点からのチェックポイント
- 内部通報制度は「社外の窓口」または「匿名で使える」ようになっているか?
- 有報やCG報告書に、通報件数や処理状況が定量的に記載されているか?
- 過去に不祥事を起こした企業が、制度をどう改善したかを具体的に開示しているか?
このような観点で企業をチェックすることで、「透明性と健全性のある企業」と「形式だけの企業」を見分けることが可能になります。
投資対象として、どちらにお金を託すべきかは明白です。
4.監査役の報告に“反省”や“再発防止”の具体策がない
企業において不祥事が発覚した際、最も注目すべきなのは「その後、何をどう改善したのか」です。
なぜなら、再発を防止する体制を整えられるかどうかが、その企業のガバナンス能力そのものを表すからです。
しかし、レオパレス21の施工不良問題における「再発防止策」の記述は、驚くほど抽象的で具体性に欠けていたことが、有価証券報告書からも明らかです。
🔍 有価証券報告書に見る「反省の抽象化」
たとえば、2019年3月期の有価証券報告書【企業統治に関する事項】では、以下のように記載されています:
「当社は、本件に関して経営責任を真摯に受け止め、ガバナンス体制の強化および内部統制システムの再構築に努めております」
一見、誠実に見える表現ですが、「何を、どう強化し、どう再構築するのか」の具体性が一切示されていません。
📉 「努力している」では意味がない
ガバナンス体制の改善というのは、本来:
- 組織構造の変更(例:独立社外取締役の追加・取締役会の構成比の見直し)
- 社内通報制度の刷新(外部通報窓口の設置・匿名通報の導入)
- 施工品質管理の再設計(外部監査の導入・第三者委員会の継続的監視)
などの具体的な制度や仕組みの導入・強化で示されるべきものです。
しかしレオパレス21のIR資料やガバナンス報告書には、それらが「表現レベル」でしか提示されていません。
その結果、「改善したフリ」に見えてしまうのは当然であり、投資家としては大きな不安材料となります。
🧾 監査役の監査報告にも同様の傾向
同じく2019年3月期の監査報告(監査役会による意見表明)では、施工不良問題への対応に触れつつも:
「経営陣に対し、再発防止策の徹底を要請した」
「今後も注視していく」
といった、行動の主体性や検証の仕組みが見えない記述にとどまっています。
これでは、監査役会が経営に対して有効な監督機能を果たしているのかどうかが判断できません。
❗ 本当にガバナンスが改善されている企業とは?
他社の良い事例と比較すると、その違いは明らかです。
たとえば、オリンパス(粉飾事件後)や大和ハウス(施工問題後)は、再発防止策として:
- 監査役の任命基準や独立性の定義
- 不正リスク管理委員会の常設化
- ガバナンスコードの具体的な遵守状況の開示
など、実行可能な仕組みレベルでの改善策を提示し、社外ステークホルダーにも透明性を持って開示しています。
📌 投資家の視点で見るべきポイント
- ガバナンス報告の「中身」は制度の名称ではなく運用と定量性
- 「努める」「注視する」といった抽象語だけの記述は改善の証明にならない
- 監査役や取締役会が改善状況をどのように検証しているかが記されているか?
レオパレス21の例は、ガバナンス体制の崩壊が「問題発覚後も継続し得る」ことを示す実例です。
投資判断の際には、単に「ガバナンスを改善したと宣言しているか」ではなく、その中身が具体的かどうかを読み解く力が求められます。
5.現在も監視体制が十分とは言えない?
施工不良問題が大々的に報道され、企業としての信頼が大きく揺らいだレオパレス21。
問題発覚後、同社は複数回にわたり「ガバナンス体制の強化」「企業統治の再構築」を公に表明してきました。
しかし、2025年時点においても、「本当に監視体制が十分に整ったのか?」という問いには疑問が残ります。
🔍 現在の取締役構成:社外取締役は形式的に増えたが…
2024年3月期の有価証券報告書によれば、同社の取締役構成は以下の通りです:
- 取締役:5名
- うち社外取締役:2名
- 監査役:3名(うち社外監査役:2名)
これは一見、東証が推奨する「取締役の3分の1以上を独立社外取締役にする」というコーポレートガバナンス・コード(以下CGコード)の原則に“形式上”は適合しています。
しかしながら、社外取締役の経歴や構成を見ると、「多様性」や「相互牽制」が十分に担保されているとは言いがたいのが実情です。
📉 社外取締役の“相互牽制”に乏しい実態
2024年6月の同社IR資料では、社外取締役の経歴として以下のような傾向が見られます:
- 不動産業界出身者、または建設業界に近い経歴者が複数
- 経営者経験や独立系弁護士、ESG分野などの専門家は不在
- 非常勤が中心で、経営判断への影響力が限定的
これは、同質性が高く、内部への批判的視点や牽制力を持ちにくい構成です。
つまり、社外取締役という制度は整っていても、「独立性」と「多様性」という本質的な要件を満たしていない状態です。
さらに、同社のCG報告書(2025年6月更新)には以下のような記述があります:
「多様性の観点から女性や外国人の取締役登用については、現時点で具体的な計画はない」
このように、形式面で“最低限”は整っていても、「進んだ企業統治」の観点からは後れを取っていることが読み取れます。
🧩 東証のCGコードとの乖離
2021年に改訂されたCGコードでは、以下のような原則が明記されています:
- 【原則4-8】独立社外取締役を複数名(できれば3分の1以上)選任すること
- 【補充原則4-11①】取締役会は多様な知識・経験・性別・国籍を考慮すべき
- 【補充原則4-9】独立性の高い社外取締役を選定するための基準を公開すること
しかし、レオパレス21の対応は:
- 数だけ合わせているが、属性の多様性には消極的
- 独立性の判断基準や個別の選任理由が不明確(IR資料・報告書上に説明不足)
このような点で、「最低限の要件は満たしているが、実質的なガバナンス強化には踏み込めていない」状態が続いていると評価せざるを得ません。
📌 投資家が見るべきチェックポイント
- 社外取締役が「誰なのか」ではなく、「何者なのか」「どう機能しているのか」
- 多様性(性別・職歴・専門性)の有無
- CG報告書で、社外取締役の選定理由や独立性基準が具体的に説明されているか?
- 取締役会の出席率や発言内容の開示状況
不祥事を経た企業にとって、ガバナンス体制の見直しは“スタートライン”にすぎません。
その後、どう運用され、どれだけ実効性のある牽制機能を果たしているかを継続的にチェックすることが、投資家にとって極めて重要です。
レオパレス21の現在の体制を見ても、「形式的には整っているが、本質的な改革には道半ば」という印象を拭いきれません。
✅ まとめ:再現できるチェックポイント
「上場企業だから安心」とは限らない。
今回見てきたレオパレス21の事例から分かるのは、ガバナンス体制の“不備”は数字に現れる前から始まっているという事実です。
投資で“危ない企業”を避けるには、企業統治を読む力=「ガバナンス・リテラシー」が不可欠です。
以下は、投資前に必ず確認すべき“再現できるチェックポイント”です。
🔍 ガバナンス・チェックリスト(事前診断用)
- 社外取締役の選定は多様性があるか?
→ 経営者経験者、法律家、会計士、ESG専門家など、「外部の視点」が機能する構成になっているか。
→ 不動産や建設出身者ばかりの“身内人事”ではないか? - 過去に不祥事があった際の対応が“具体的”か?
→ 「真摯に受け止める」ではなく、「どう組織を変えたのか」が書かれているか?
→ IR資料やガバナンス報告に仕組みレベルでの再発防止策があるか? - 監査役・取締役会が“何もしていない”ように見えないか?
→ 有価証券報告書に「取締役会としての対策」や「社外監査役の意見」が具体的に記載されているか?
→ “注視していく”などの抽象表現で終わっていないか?
📌 上記の項目を、企業の【有価証券報告書】や【ガバナンス報告書】を通じて確認するだけでも、
表面では分からない「ガバナンスの健全性」を見抜く力が身につきます。
✅ 投資判断に「仕組み」を持ち込もう
ほとんどの投資初心者が、企業を「株価」や「配当」だけで判断しがちです。
しかし、実際に長期でリターンを得ている投資家は、「数字の裏側」にある統治構造・人的構成を重視しています。
あなたが今日から投資判断を“レベルアップ”するなら、
「ガバナンスを自分で読み解く」ことから始めてください。
✋ 最後にひと言
「問題が起きたときに、初めて異変に気づく」――それでは遅いのです。
問題が起きる前に“企業の内部構造”を読み取れる人が、投資で勝ち残る人です。
このチェックリストを、あなたの投資判断の“定規”として活用してください。
📚 参照データ一覧
🔸 報道・メディア証言
- 「レオパレス施工不良、社内で10年前から認識か」
発行:朝日新聞、2018年3月1日付
内容:レオパレス元社員の証言に基づき、2007年ごろから施工不良の内部認識があったと報道。 - 「レオパレス問題の深層 ~追い詰められた建築業界~」
発行:NHK クローズアップ現代+、2019年3月放送
内容:施工不良に関する社内黙認の構造や、元社員の証言などを取り上げた特集番組。 - 「第三者委員会調査報告書(概要)」
発行:株式会社レオパレス21、2019年3月発表(※現在は非公開)
内容:内部通報制度の機能不全、監査体制の問題、経営陣の責任に関する指摘が盛り込まれた。
🔸 公的資料・ガバナンス関連基準
- 「株式会社レオパレス21 有価証券報告書(2023年3月期、2024年3月期)」
発行:金融庁EDINET
内容:取締役構成、監査役コメント、ガバナンス体制の詳細記載。 - 「株式会社レオパレス21 コーポレート・ガバナンス報告書(2024年6月提出)」
発行:東京証券取引所
内容:CGコードへの対応状況、社外取締役の選任理由と独立性の記述あり。 - 「コーポレート・ガバナンス・コード(2021年改訂版)」
発行:日本取引所グループ(JPX)
内容:原則4-8(社外取締役)、原則4-9(独立性判断基準)、補充原則4-11(多様性)など。 - 「企業価値向上に資するガバナンスのあり方研究会 報告書」
発行:経済産業省、2020年
内容:社外取締役・監査役の役割、企業統治の課題と改善の方向性について提言。